九電健保被扶養者認定の取扱い
健康保険組合は、被保険者に扶養されている家族(認定対象者)について、被保険者からの届出により、認定対象者を健康保険法や厚生労働省通知等で示されている一定の条件に基づき、社会通念等にも照らした総合的な審査を行い、被扶養者として認定するかを決定します。
当健保組合の被扶養者認定の取扱いについて、以下のとおりまとめていますのでご活用ください。
- (1)被扶養者の範囲
- (2)生計維持確認が必要な認定対象者
- (3)被保険者が優先扶養義務者であること
- (4)収入がある認定対象者
- (5)事業収入がある認定対象者
- (6)仕送り基準
- (7)夫婦共同扶養
- (8)両親(夫婦)の認定
- (9)被扶養者の資格調査(検認)
- (10)認定日
- 被扶養者認定の際の提出書類一覧
- 被扶養者認定フローチャート
- 九州電力健康保険組合が認める「直接的必要経費」一覧表
- 仕送りについてQ&A
(1)被扶養者の範囲
健康保険法第3条第7項により、範囲は次のとおり規定されています。
なお、「後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人等)」は、被扶養者にすることができません。
| 被保険者との同居・別居どちらでもよい人 | 被保険者との同居が条件となる人 |
|
|
|---|
- ※被保険者の直系尊属には、父母の内縁関係にある人、配偶者の直系尊属は含みません。
- ※内縁関係の配偶者とは、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人をいいます。
- ※子とは、民法上の実子および養子をいい、養子縁組をしない配偶者の子および子の配偶者は含みません。
- ★同居(同一世帯=住民票同一)
被保険者が世帯主である必要はありませんが、被保険者と住居および家計を共にしている状態を指します。また、世帯分離(同一の住所に世帯主が二人)の場合、別居扱いとなります。
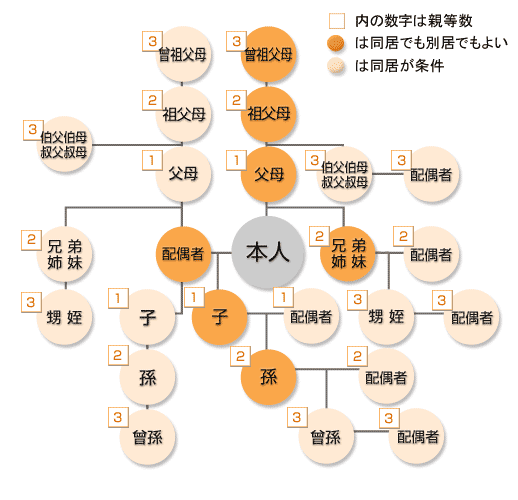
(2)生計維持確認が必要な認定対象者
被保険者との関係および生計維持関係の確認については、原則として公的証明書等にて行うこととされています。
なお、16才未満の人と16才以上の学生については、生計維持確認の書類を省略することが可能となっています。
被保険者は、被扶養者を有する場合には、被扶養者異動届に認定審査に必要な書類を添付して、事業主経由で当健保組合へ提出します。
被保険者との関係および生計維持確認の書類
| 確認項目/ 申請対象者 |
被保険者との 関係(続柄) 確認書類 |
生計維持確認書類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 収入確認 (※1) |
同居 (同一世帯) |
別居 (仕送り確認) |
|||
| 出生児 | 住民票または 出生証明書 |
不要 | 不要 | 不要 | |
| 16才未満 | 住民票または 戸籍謄本 |
不要 | 住民票 | 不要 | |
| 16才以上 (※2) |
学生 | 住民票または 戸籍謄本 |
在学証明書 | 住民票 | 不要 |
| 学生以外 | 住民票または 戸籍謄本 |
所得証明書 | 住民票 | 要 | |
- (※1)夫婦共働きの子女の場合、両親の収入確認書類の提出が別途必要です。
- (※2)16才以上の認定対象者については、扶養理由書の提出が必要です。
- POINT
-
- 16才以上の学生については、在学証明書の提出により、生計維持確認の書類は免除されます。ただし、被扶養者資格調査時において、アルバイト収入等で収入基準額を超過していることが判明した場合は、扶養から外れていただきます。
- その他の認定審査に必要な書類は「被扶養者認定の際の提出書類一覧」を参照ください。
(3)被保険者が優先扶養義務者であること
原則として被保険者が認定対象者の優先扶養義務者(※)であることが必要です。
ただし、認定対象者に被保険者以外の優先扶養義務者がいる場合には、その優先扶養義務者の収入および扶養能力、同居の有無、被保険者が認定対象者を扶養せざるを得ない理由、生計維持の事実などを総合的に勘案した上で、被保険者が先順位の扶養義務者であるかを判断します。
なお、被保険者が家庭裁判所の審判で認定対象者の扶養の義務を負わされている場合は、被保険者を先順位の扶養義務者として取り扱います。
(※)優先扶養義務者とは、以下のとおりです。
- 認定対象者の「配偶者」(例:認定対象者が母の場合は「父」)
- 認定対象者が「兄弟姉妹」の場合は「両親」
- 認定対象者が「孫」の場合は「子(孫の両親)」
- POINT
-
- 原則として、同居をもって先順位の扶養義務者としていましたが、「原則として被保険者が認定対象者の優先扶養義務者であること」に見直しました。
- 認定対象者に被保険者以外の優先扶養義務者がいる場合には、同居の有無や扶養義務者の収入や扶養能力等を、総合的に勘案した上で、被保険者が先順位の扶養義務者であるかを判断します。
- 認定対象者が「配偶者」および「子」以外の場合は、被保険者が優先扶養義務者であるかを判断するため、「被扶養者認定基準チェック表(配偶者・子以外の申請)」の提出が必要です。(認定対象者が無収入の場合でも提出ください)
- 「被扶養者認定フローチャート」をご活用ください。
- 被扶養者認定に関する書類は、当健保組合ホームページ(申請書一覧)をご確認ください。
(4)収入がある認定対象者
被扶養者として認定されるには、「主として被保険者により生計を維持されていること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。
この「主として被保険者により生計を維持されている」とは、被保険者の収入により認定対象者の生計費(食費、住居費、光熱・水道費等)の2分の1以上を、継続的に将来に向かって賄われている状態をいい、具体的には次の条件に基づき「被扶養者認定基準チェック表」により判断します。
| 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合 |
|---|
| 認定対象者の年間収入が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること |
| 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合 |
|---|
| 認定対象者の年間収入が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であって、かつ、その額が被保険者からの仕送り額より少ないこと |
- ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定します(注)年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されますのでご留意ください。
- POINT
-
- 年間収入の判定については、2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の年齢要件が追加されました。
- 「被扶養者認定基準チェック表」を参照ください。
- 認定対象者が「配偶者」および「子」以外の場合は、被保険者が優先扶養義務者であるかを判断するため、「被扶養者認定基準チェック表(配偶者・子以外の申請)」の提出が必要です。(認定対象者が無収入の場合でも提出ください)
- 被扶養者認定に関する書類は、当健保組合ホームページ(申請書一覧)をご確認ください。
(5)事業収入がある認定対象者
収入の範囲
基本的に「収入」とは、金銭等で得られるもの全てを指し、下表に掲げるようなものは、全て収入と見なします。なお、当健保組合では、「退職金、企業年金、個人年金」は、収入の範囲には含みません。
| 給与収入 | 賃金、給与、手当、賞与等(通勤交通費を含む) |
|---|---|
| 各種年金 | 老齢・遺族・障害等の公的年金 |
| 各種給付 | 雇用保険の給付金(失業給付または傷病手当)、健康保険からの傷病手当金および出産手当金 |
| 事業(営業、農業)収入 | 「総収入額」から「当健康保険組合が認める必要経費」を差し引いた残りの額を収入額とします |
| 不動産、利子、配当、雑、譲渡収入 | 「総収入額」から「当健康保険組合が認める必要経費」を差し引いた残りの額を収入額とします |
| その他 | 被保険者以外の者からの仕送り(生計費、養育費等)、その他継続性のある収入 |
- POINT
-
- 事業(営業、農業)収入、および不動産収入等において、総収入額から差し引くことができる必要経費を、所得税法上の必要経費から「当健康保険組合が認める直接的必要経費」に見直しました。
- 収入から差し引くことができる経費は、「九州電力健康保険組合が認める直接的必要経費一覧表」を参照ください。
(6)仕送り基準
別居の親族の認定の場合(認定対象者と被保険者の住民票が異なっている場合)、被保険者からの仕送り(送金)が、その認定対象者の生計維持の中心的役割を果たしていることが認定要件となり、具体的には、認定対象者の収入以上の仕送りが必要となります。
仕送り頻度、仕送り証明書
詳しくは、「仕送りについてQ&A」をご確認ください。
| 仕送り頻度 | 毎月(毎月行うことが難しい場合は2か月に1回以上) |
|---|---|
| 仕送り証明書 | 銀行・郵便局の振込依頼書、払込票、利用明細書等の「客観的に誰から誰へ、いつ、いくら送金したか」が分かるもの
|
次に該当する人は、別居であっても仕送り証明書の提出が省略できます
- 別居している配偶者、別居している配偶者と同居の親族
- 通学のため別居している学生(在学証明書が必要)
- 介護施設等に入所中の親族(施設入所証明書が必要)
- ※単身赴任に伴う別居、別居の学生、施設入所の場合は一時的な別居とみなし、仕送り証明書の提出が省略できます。ただし、従来から被保険者と別居していた認定対象者については、仕送り証明書の省略はできません。
なお、施設入所で被保険者により生計を維持されていない場合(入所者自身の貯蓄や公的補助等で生計費の2分の1以上が賄われている等)は、被扶養者として認定できません。
次の場合は、被扶養者の収入以上の仕送りがあっても、被扶養者として認められません
- 被保険者より被扶養者の収入が多い場合
「被保険者の収入-送金額」<「被扶養者の収入+送金額」 - 被扶養者の収入と被保険者の送金額の合計が極端に少ない場合
(社会通念上妥当性を欠くような場合)
- ※個別判断となるため、当健保組合での審査に必要な書類をご提出いただく場合があります。
(7)夫婦共同扶養
夫婦共働きにおける子の扶養は、原則として、年間収入(※)の多い方の被扶養者とします。(※過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)
収入が同程度の場合
夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の一割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすることができます。
育児休業等期間中の場合
主として生計を維持する者が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位の観点から、特例的に被扶養者を異動しないこととします。ただし、新たに誕生した子については改めて認定手続きを行ってください。
収入が逆転した場合の扶養変更
夫婦の年間収入の逆転に伴い被扶養者を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の保険者が扶養認定したことを確認してから、被扶養者を削除する手続きを行ってください。
夫婦の一方が共済組合の組合員の場合
共済組合の組合員に、被扶養者手当等の支給が認定されている場合には、その認定を受けている方の被扶養者とすることができます。
提出書類
夫婦共同扶養における扶養申請の場合は、通常の書類に加えて、次の書類も提出してください。
| 被扶養者異動届に添付する収入比較書類 | |
|---|---|
| 被保険者の資格取得に伴う被扶養者認定 |
|
| 夫婦の一方が育児休業を取得する場合 |
|
| 配偶者が離職している場合 |
|
| 配偶者の保険者から否認された場合 |
|
- ※配偶者が国民健康保険の被保険者の場合は、配偶者の収入比較書類は「直近の所得証明書」を添付してください。
- ※被扶養者認定に関する書類は、当健保組合のホームページをご確認ください。
その他の取扱い
- 被扶養者として認定しない場合には、当該決定に係る通知(不認定通知)を発出します。
- 他保険者等が発出した不認定通知とともに被扶養者異動届を受理した場合において、他保険者等の決定に疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間および土日祝日は除く)に、不認定に係る通知を発出した他保険者等と、夫婦どちらの被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかにした上で協議します。
- (7)夫婦共同扶養の取扱いは続柄により対象が限定されないことから、子以外にも適用されます。
(8)両親(夫婦)の認定
認定対象者に配偶者がいる場合の認定については、一律に「夫婦一体」として、被扶養者に該当するか否かを判断せず、認定対象者1人の年間収入額で認定可否を判断します。
認定対象者個々の年収で判定しますので、収入が基準額以内で被保険者が優先扶養義務者であると認められれば認定されます。
【例】
64歳の父:年収200万円
59歳の母:年収90万円
- →父は収入が基準額を超えているため、認定できませんが、母は収入が基準額(60歳未満130万円未満)以内のため、その他の認定要件を満たしていれば認定されます。
(9)被扶養者の資格調査(検認)
当健保組合では、健康保険法施行規則第50条および厚生労働省保険局長通知に基づき、過去に認定した被扶養者がその後も認定基準を満たしているかを確認するため、毎年、被扶養者の資格調査を実施しています。
なお、調査の結果、被扶養者資格を満たさない場合は、事実発生日または当健保組合が定める日に被扶養者資格を削除します。なお、この場合も「被扶養者異動届」により減員申請が必要です。
- (1)調査対象者
実施の都度、決定 - (2)実施方法
調査対象者全員について、「被扶養者認定の際の提出書類」に準じた必要書類を提出いただきます。
- 健康保険法施行規則第50条(一部抜粋)
- 1 保険者(健康保険組合等)は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新または被扶養者に係る確認をすることができる。
- 2 事業主は、前項の検認若しくは更新または被扶養者に係る確認のため、被保険者証または被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
- 3 被保険者は、前項の規定により被保険者証または被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。
(中略) - 7 第一項の規定により検認または更新を行った場合において、その検認または更新を受けない被保険者証は、無効とする。
- 厚生労働省保険局長通知(保発第1029004号)
- 1 被保険者証の検認については、保険給付の適正化の観点から、毎年実施すること。
(10)認定日
被扶養者の認定においては、増員申請(扶養に入れる場合)・減員申請(扶養から外す場合)ともに「事由発生日」が起点となります。
増員申請の場合は「事由発生日=認定日」、減員申請の場合は「事由発生日=削除日」となり、原則として、事由発生日から5日以内に「被扶養者(異動)届」による申請が必要となります。
増員申請(主なもの)
| 事由 | 事由発生日 |
|---|---|
| 被保険者の入社 | 採用の日(被保険者の資格取得日) |
| 結婚 | 婚姻届受理日 |
| 出生 | 出生の日 |
| 離職 | 離職日の翌日 |
| 失業給付受給終了 | 受給終了日の翌日 |
| 養子縁組 | 戸籍記載の縁組日 |
| 同居 | 住民票記載の同居日 |
| 扶養変更 | 状況により異なります。 |
| その他の理由 | 被扶養者異動届の受理日 |
減員申請(主なもの)
| 事由 | 事由発生日 |
|---|---|
| 就職 | 就職した日(就職先の保険証の資格取得年月日) |
| 子等の結婚 | 婚姻届受理日 |
| 離婚 | 戸籍記載の離婚日 |
| 死亡 | 死亡日の翌日 |
| 別居 | 住民票記載の別居日 |
| 失業給付受給開始 | 受給開始日 |
| 年間収入超過 | 収入限度額を超えた日 |
| その他の理由 | 被保険者により生計を維持されなくなった日 |
増員申請時の認定日の取扱い
当健保組合では、増員申請の場合、添付書類等を取り寄せる時間等を考慮して、事由発生日から1か月以内に「被扶養者(異動)届」を受理した場合に限り、事由発生日まで遡って認定します。
| 被扶養者(異動)届の受理日(※1) | 認定日 |
|---|---|
| 事由発生日から1か月(※2)以内 | 事由発生日まで遡り認定 |
| 事由発生日から1か月(※2)を経過 | 被扶養者(異動)届の受理日(※1)で認定 |
- ※1:当健保組合にて添付書類等がすべて確認できたときが受理日となります。
- ※2:1か月の満了日が当健保組合休業日の場合は、その前日までとなります。
被扶養者認定の際の提出書類一覧
被扶養者認定フローチャート
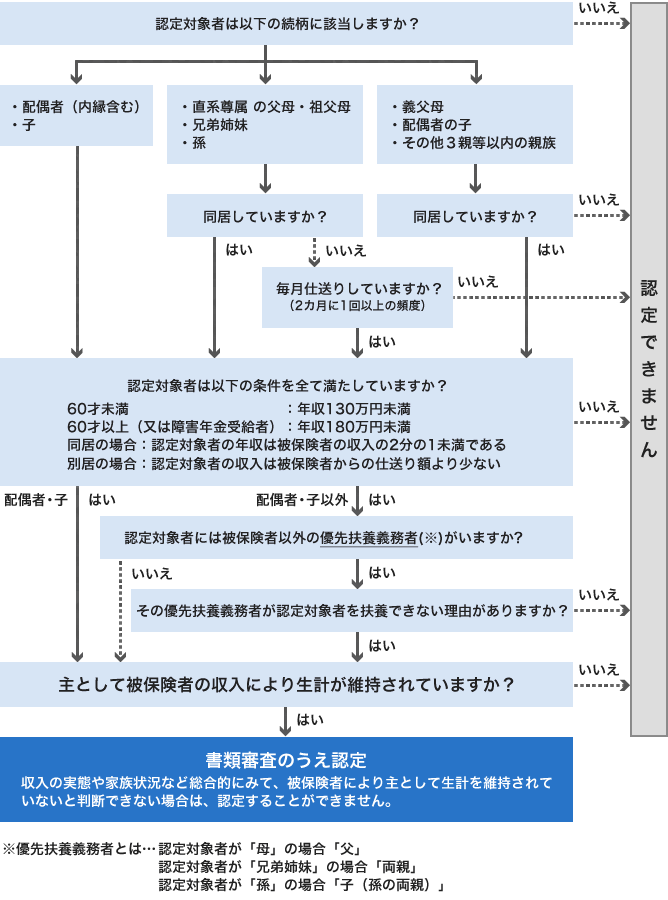
九州電力健康保険組合が認める「直接的必要経費」一覧表
仕送りについてQ&A
- Q1仕送りは、毎月行う必要がありますか。
- A1扶養家族に対し、生活費として仕送りを行っているのであれば、毎月行うことが望ましいと思われます。ただし、毎月行うことが難しい場合は、2か月に1回以上の仕送りを行い、生計を維持できる金額を送金してください。(継続的に生計維持の中心的役割を果たしていることを扶養認定の条件としているため、賞与での一括の送金は認められません。)
- Q2すでに認定中の被扶養者と別居になった場合の取扱いはどうなりますか。
- A2毎年実施の被扶養者資格調査時に仕送り証明が提出できるよう、仕送り証明書を保管しておいてください。なお、提出ができない場合は、被扶養者として認定できません。(被扶養者の減員手続きが必要です)
- Q3別居している被扶養者が、学生の場合も仕送り証明の提出が必要ですか。
- A3別居している学生の場合は、一時的な別居とみなすため、仕送り証明の提出は必要ありません。
- Q4別居とは具体的にどういう範囲ですか。
- A4住所が同じ(同一敷地内、2世帯住宅)でも、住民票が異なっていれば別居とみなします。
- Q5同一口座(同一名義)の通帳とキャッシュカードでやり取りしている場合は、どのような書類が必要になりますか。
- A5通帳・キャッシュカードで直接入金する方法では、「客観的に誰から誰への振込か」を証明できないため、認められません。送金方法を見直し、客観的に仕送りの事実が確認できる書類を提出ください。
- Q6金融機関等を経由しての送金ができない場合はどうすればよいですか。
- A6客観的に仕送りの事実が確認できる書類の提出が必要となります。そのため、金融機関等を経由しての送金ができない場合は被扶養者として認定できません。(被扶養者の減員手続きが必要です)
- Q7被扶養者である両親と同居の従業員(独身)が、転勤のため両親と別居とすることになりました。この場合、単身赴任に伴う一時的な別居とみなされ、仕送り証明書の提出は免除されますか。
- A7当健保組合においての、単身赴任による一時的な別居としてみなされる人は、①別居している配偶者②別居している配偶者と同居の親族となっています。ご質問のケースは上記①②に該当しないため、両親への仕送り証明書の提出は必要となります。





